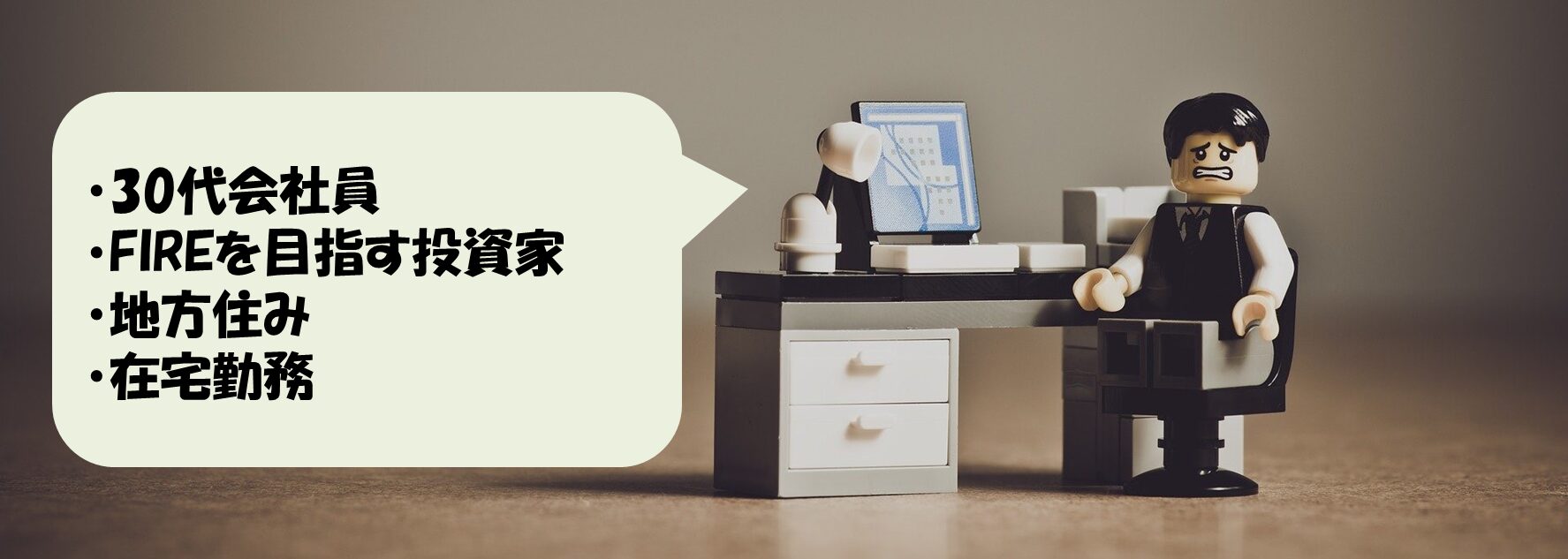近年、日本国内でも個人投資家の間で人気を博していたソーシャルレンディング。しかし、2020年代前半に起こった一連の問題や業界再編を経て、「ソーシャルレンディングはもう終わった」と言われることも増えてきました。果たして、それは本当なのでしょうか? 本記事では、2025年現在のソーシャルレンディング市場の実態と、投資家が取るべき判断を徹底的に掘り下げていきます。
ソーシャルレンディングとは?簡単なおさらい
ソーシャルレンディングとは、資金を必要とする企業や個人と、利回りを求める投資家をマッチングするクラウド型融資の仕組みです。従来の銀行融資とは異なり、プラットフォームを通じて多数の投資家から少額ずつ資金を集めて融資が行われます。
- 平均利回り:4〜8%
- 運用期間:6ヶ月〜3年
- 主な投資先:不動産、事業融資、新興国ローンなど
詳しくは、マイナーな投資の世界 もご覧ください。
ソーシャルレンディングが「オワコン」と言われる理由
1. 過去の不祥事と信頼低下
maneoやグリーンインフラレンディングなど、複数のソーシャルレンディング事業者が過去に不正融資や返済遅延を起こし、行政処分や撤退に追い込まれました。これにより、「怪しい投資先」として認識されるようになったのは否めません。
2. 参入業者の減少とプラットフォームの縮小
2021年以降、多くの事業者が新規案件を停止、または事業撤退を行っています。健全な市場の再構築が進んではいますが、選択肢が狭まり、投資家の興味は他の分野(高配当株やETFなど)へと移行しつつあります。
3. 他の投資手段に埋もれる存在に
最近では、新NISA制度の後押しもあり、株式・ETFへの投資人気が急上昇しています。ソーシャルレンディングのような「ハイリスク・中リターン」の投資商品は相対的に魅力が薄れている面もあります。
それでもソーシャルレンディングに投資するメリット
1. 株式と異なる値動き
ソーシャルレンディングは株価や為替の影響を受けにくく、ポートフォリオの分散先として一定の価値があります。
2. インカムゲイン重視の人に向いている
毎月あるいは四半期ごとの分配金が得られる点は、楽天SCHDなどと似た魅力です。
3. 利回りの高さ
うまく案件を選べば、5%以上の利回りも狙えます。ただし、リスク管理が不可欠です。
2025年現在、注目されているソーシャルレンディングプラットフォーム
- Funds(ファンズ):大手企業と連携しており、透明性が高い
- クラウドバンク:国内外の案件に分散可能で運用実績も豊富
- CREAL:不動産特化型で利回りと安定性のバランスが良好
これらの事業者は金融庁の登録業者であり、過去の教訓からコンプライアンスを強化しています。
ソーシャルレンディングに代わる注目の投資先
最近では以下のような投資商品も注目されています。
- レバレッジ型ETF
- 金(ゴールド)への分散投資
- 不動産クラウドファンディング
- トークン証券(セキュリティトークン)
これらはソーシャルレンディングの「利回り志向」と「非株式資産」という性質を持ちつつ、より制度的に整備されています。
結論:ソーシャルレンディングは「オワコン」ではないが、慎重な選択が必要
ソーシャルレンディング市場は確かに一時期より縮小し、投資家の関心も分散しています。しかし、それは「終わった」というよりも、「淘汰された」と表現する方が正確かもしれません。
今後も信頼できる事業者が提供する案件に限定して分散投資することで、十分なリターンを得ることは可能です。あくまで全体ポートフォリオの一部として位置づけ、無理のない範囲で取り入れるのが現実的な戦略です。
関連リンク